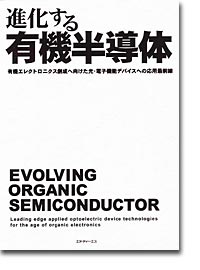| |
| 筒井哲夫 | 九州大学大学院総合理工学研究院 教授 |
| 古川行夫 | 早稲田大学理工学部 教授 |
| 金藤敬一 | 九州工業大学大学院生命体工学研究科 教授 |
| Anil Kumar Thakur | 九州工業大学大学院生命体工学研究科 博士研究員 |
| 赤木和夫 | 筑波大学大学院数理物質科学研究科 教授/学際物質科学研究センター長 |
| 飯田洋 | 筑波大学大学院数理物質科学研究科 博士課程 |
| 倉本憲幸 | 山形大学大学院理工学研究科 教授 |
| 大坪徹夫 | 広島大学大学院工学研究科 教授 |
| 瀧宮和男 | 広島大学大学院工学研究科 助教授 |
| 奥本肇 | 独立行政法人産業技術総合研究所ナノテクノロジー研究部門分子ナノ物性グループ 主任研究員 |
| 南信次 | 独立行政法人産業技術総合研究所ナノテクノロジー研究部門 副部門長 |
| 青山哲也 | 独立行政法人理化学研究所和田超分子科学研究室 研究員 |
| 和田達夫 | 独立行政法人理化学研究所和田超分子科学研究室 主任研究員 |
| 青田浩幸 | 関西大学工学部応用化学科 助教授 |
| 松本昭 | 関西大学工学部応用化学科 教授 |
| 生駒忠昭 | 東北大学多元物質科学研究所 助手 |
| 手老省三 | 東北大学多元物質科学研究所 教授 |
| 河合壯 | 奈良先端科学技術大学院大学物質科学教育研究センター 教授 |
| 佐々木孝彦 | 東北大学金属材料研究所 助教授 |
| 荒木圭一 | 信州大学繊維学部 研究員 |
| 市川結 | 信州大学繊維学部 助手 |
| 谷口彬雄 | 信州大学繊維学部 教授 |
| 御崎洋二 | 愛媛大学工学部 教授 |
| 阪元洋一 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構分子科学研究所分子スケールナノサイエンスセンター 助手 |
| 鈴木敏泰 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構分子科学研究所分子スケールナノサイエンスセンター 助教授 |
| 原本雄一郎 | 山梨大学大学院医学工学総合研究部 教授 |
| 岡畑恵雄 | 東京工業大学フロンティア創造共同研究センター 教授/大学院生命理工学研究科 教授 |
| 川崎剛美 | 東京工業大学大学院生命理工学研究科 助手 |
| 村田滋 | 東京大学大学院総合文化研究科 助教授 |
| 荒金崇士 | 出光興産株式会社電子材料部EL開発センターELソリューションチーム |
| 飛田道昭 | ヒロセエンジニアリング株式会社研究開発室 リーダー/参事 |
| 石飛達郎 | ヒロセエンジニアリング株式会社研究開発室 主事 |
| 枝連一志 | ヒロセエンジニアリング株式会社研究開発室 主事 |
| 仲矢忠雄 | ヒロセエンジニアリング株式会社 常務取締役研究開発室長/大阪市立大学名誉教授 |
| 小林範久 | 千葉大学大学院自然科学研究科 教授 |
| 佐藤宗英 | 慶應義塾大学大学院基礎理工学専攻 大学院生 |
| 山元公寿 | 慶應義塾大学理工学部 教授 |
| 都築俊満 | 日本放送協会放送技術研究所 |
| 鈴木充典 | 日本放送協会放送技術研究所 |
| 時任静士 | 日本放送協会放送技術研究所 主任研究員 |
| 高木幸治 | 名古屋工業大学大学院工学研究科 助教授 |
| 三上明義 | 金沢工業大学工学部 電気系副主任/教授 |
| 安達千波矢 | 九州大学未来化学創造センター 教授 |
| 中野谷一 | 千歳科学技術大学大学院光科学研究科 |
| 夛田博一 | 大阪大学大学院基礎工学研究科 教授 |
| 八尋正幸 | 日本放送協会放送技術研究所(現在、九州大学未来化学創造センター) |
| 柳嶋延欣 | 東京理科大学理学部 |
| 池畑誠一郎 | 東京理科大学大学院理学研究科 教授 |
| 大森裕 | 大阪大学先端科学イノベーションセンター先端科学技術インキュべーション部門 教授 |
| 上原赫 | 京都大学エネルギー理工学研究所 客員教授/大阪府立大学名誉教授 |
| 吉川暹 | 京都大学エネルギー理工学研究所 教授 |
| 當摩哲也 | 独立行政法人産業技術総合研究所太陽光発電研究センター有機薄膜チーム 研究員 |
| 斉藤和裕 | 独立行政法人産業技術総合研究所太陽光発電研究センター有機薄膜チーム チーム長 |
| 谷垣宣孝 | 独立行政法人産業技術総合研究所光技術研究部門デバイス機能化技術グループ 研究グループ長 |
| 溝黒登志子 | 独立行政法人産業技術総合研究所光技術研究部門デバイス機能化技術グループ 研究員 |
| 望月博孝 | 独立行政法人産業技術総合研究所光技術研究部門ガラス材料技術グループ 研究員 |
| 平賀隆 | 独立行政法人産業技術総合研究所光技術研究部門 総括研究員 |
| 瀬川浩司 | 東京大学大学院総合文化研究科 助教授 |
| 折原勝男 | 山形大学工学部 助教授 |
| 譚迺迪 | 山形大学大学院理工学研究科 博士後期課程3年 |
| 直井勝彦 | 東京農工大学大学院共生科学技術研究部 教授 |
| 荻原信宏 | 東京農工大学大学院共生科学技術研究部 助手 |
| 工藤康夫 | 元松下電子部品株式会社 |
| 小野田光宣 | 兵庫県立大学大学院工学研究科 教授 |
| 奥崎秀典 | 山梨大学大学院医学工学総合研究部 助教授 |
| 中本裕之 | 兵庫県立工業技術センターものづくり開発部情報技術担当 研究員 |
| 久保井亮一 | 大阪大学大学院基礎工学研究科 教授 |
| 島内寿徳 | 大阪大学大学院基礎工学研究科 助手 |
| 大川祐司 | 独立行政法人物質・材料研究機構ナノマテリアル研究所 主幹研究員 |
| 青野正和 | 独立行政法人物質・材料研究機構ナノマテリアル研究所 所長 |
| 居城邦治 | 北海道大学電子科学研究所 教授 |
| 芥川智行 | 北海道大学電子科学研究所 助教授 |
| 中村貴義 | 北海道大学電子科学研究所 教授 |
| 坂口浩司 | 静岡大学電子工学研究所 助教授/独立行政法人科学技術振興機構さきがけ |
| 下村武史 | 東京農工大学大学院共生科学技術研究部 助教授 |
| 伊藤耕三 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 |
| 石津浩二 | 東京工業大学大学院理工学研究科 教授 |
| 藤木道也 | 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科 教授 |
| 笠井均 | 東北大学多元物質科学研究所 助教授 |
| 及川英俊 | 東北大学多元物質科学研究所 助教授 |
| 中西八郎 | 東北大学多元物質科学研究所 教授 |
| |
| はじめに 有機エレクトロニクス〜大きな期待と現実の壁・そして今何をなすべきか〜 |
|
| 1 | 有機半導体のルネッサンス |
| 2 | なぜ、有機半導体 |
| 3 | 無機半導体から有機半導体へ、パラダイムシフト |
|
| 基礎編 有機半導体の科学 |
|
| 1 | 導電性高分子&オリゴマー系有機半導体 |
| 1.1 | 導電性高分子の分子構造と電気伝導理論 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 分子構造 |
| 3 | バンド理論 |
| 4 | 吸収スペクトルと励起子効果 |
| 5 | 素励起 |
| 6 | 電気伝導 |
|
| 1.2 | 導電性高分子の電気伝導特性と計測法 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 導電性高分子の電気的特性 |
| 3 | 導電率の測定法 |
| 4 | 電極との接触 |
| 4.1 | 導電性が高い材料の電導率の測定方法 |
| 4.2 | 絶縁性材料の電導度の測定 |
| 5 | おわりに |
|
| 1.3 | 導電性高分子高機能化分子設計〜キラル液晶性導入を中心に〜 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 側鎖にキラル置換基を有する主鎖型液晶性芳香族共役系高分子 |
| 2.1 | ポリマーの合成と性質 |
| 2.2 | 円偏光二色性スペクトル |
| 2.3 | 円偏光蛍光スペクトル |
| 3 | キラル化合物の添加による側鎖型液晶性芳香族共役系高分子へのキラリティ誘起 |
| 3.1 | 液晶性ポリパラフェニレン誘導体とキラル化合物の性質 |
| 3.2 | 液晶性ポリパラフェニレン誘導体へのキラル化合物の添加 |
| 3.3 | 円偏光蛍光スペクトルの測定 |
| 4 | まとめ |
|
| 1.4 | ポリアニリンの高機能化分子設計 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 配向組織中におけるアニリンの重合による加工性の良好なポリアニリンの合成と応用 |
| 3 | 二酸化チタンとポリアニリンを電極にした湿式太陽電池 |
| 4 | ポリアニリン誘導体を分散質とするエレクトロレオロジー流体(ER流体) |
| 5 | 二酸化チタンと複合加熱処理によるポリアニリンの導電性向上 |
| 6 | らせん構造光学活性ポリアニリン誘導体の合成と性質 |
| 7 | ポリアニリンの活性酸素発生能に関する研究 |
| 8 | ポリアニリンの酸化還元による伸張収縮現象を利用した人工筋肉アクチュエータ |
|
| 1.5 | オリゴチオフェンの高機能化設計 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 長鎖オリゴチオフェンの開発 |
| 3 | 有機薄膜トランジスタ材料としてのオリゴチオフェン |
| 4 | 電界発光材料としてのオリゴチオフェン |
| 5 | 光電変換材料としてのオリゴチオフェン |
| 6 | オリゴチオフェン自己集合単分子膜の光電変換素子 |
| 7 | おわりに |
|
| 1.6 | オリゴシラン自己組織化膜の電荷輸送特性 |
| 1 | はじめに |
| 2 | オリゴシラン自己組織化膜の作製法と構造 |
| 3 | 自己組織化薄膜の構造と電荷輸送特性 |
| 3.1 | 理想的な光過渡応答電流波形 |
| 3.2 | キャリア移動度の温度・電場依存性 |
| 3.3 | オリゴシラン主鎖長に依存する電荷輸送特性 |
| 3.4 | オリゴシラン末端基長に依存する電荷輸送特性 |
| 3.5 | ホッピング伝導の素過程を反映した単純な電荷輸送モデル |
| 4 | おわりに |
|
| 1.7 | 高い電荷移動度を有す共役系有機半導体の開発 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 電荷輸送材料 |
| 3 | 電荷輸送モデル |
| 4 | 高移動度発現の材料設計 |
| 4.1 | 共役系の拡張 |
| 4.2 | ガラス転移温度 |
| 5 | 電界効果移動度 |
| 6 | おわりに |
|
| 1.8 | 水溶性狭バンドギャップポリマーの合成 |
| 1 | 狭バンドギャップポリマーの現状 |
| 2 | 天然の共役系分子“ポルフィリン" |
| 3 | 水溶性狭バンドギャップポリマーの合成 |
| 3.1 | 非共役系ポリマーの合成 |
| 3.2 | 共役系の形成 |
| 3.3 | 狭バンドギャップ化の条件 |
| 4 | 水溶性狭バンドギャップポリマーの物性 |
| 5 | まとめ |
|
| 1.9 | 光導電性高分子と導電機構とその機能 |
| 1 | はじめに |
| 2 | キャリアの生成と輸送過程 |
| 3 | 再結合・キャリア生成収率に対する磁場効果の機構 |
| 4 | 正孔移動メカニズム |
| 5 | 励起三重項状態からのキャリア生成 |
| 6 | ホッピング機構とOnsagerモデル |
| 7 | おわりに |
|
| 1.10 | フォトクロミック分子によるπ共役系分子鎖の光機能化 |
| 1 | はじめに |
| 2 | フォトクロミック分子による光スイッチング |
| 3 | フォトクロミック分子による導電性高分子光スイッチ |
|
| 2 | 低分子系有機半導体 |
| 2.1 | 有機半導体の金属―絶縁体転移 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 金属状態と絶縁体状態 |
| 3 | モット絶縁体と電荷秩序絶縁体 |
| 4 | BEDT―TTF系有機導体の金属―絶縁体転移 |
| 5 | k―(BEDT―TTF)2Xでのモット金属―絶縁体転移 |
|
| 2.2 | 有機半導体レーザの基礎と分子設計 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 有機半導体レーザの基礎 |
| 2.1 | レーザ発振のメカニズム |
| 2.2 | 共振器 |
| 3 | OLED型レーザ |
| 4 | 有機単結晶レーザ |
| 5 | おわりに |
|
| 2.3 | 高導電性および超伝導性電荷移動錯体の高性能化と分子設計 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 有機分子性金属の開発指針 |
| 3 | TTP系導体 |
| 3.1 | 合成および酸化還元特性 |
| 3.2 | TTP塩の構造と物性 |
| 3.3 | 新しい超伝導体(DTEDT)3Au(CN)2 |
| 3.4 | 三次元的な分子配列を有するTTP系導体 |
| 4 | おわりに |
|
| 2.4 | π共役系有機半導体〜n型半導体を中心に〜 |
| 1 | はじめに |
| 2 | シアノ基を有する化合物 |
| 3 | フラーレンとその誘導体 |
| 4 | フッ素置換化合物 |
| 5 | ナフタレンおよびペリレンテトラカルボン酸ジイミド誘導体 |
| 6 | オリゴチオフェンおよびチアゾール誘導体 |
| 7 | おわりに |
|
| 2.5 | 液晶半導体 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 液晶とは |
| 3 | 液晶半導体の原理 |
| 4 | 電圧―電流特性について |
| 5 | 新規なメモリ : 導電性スポットメモリ |
|
| 3 | バイオマテリアル |
| 3.1 | DNA配向化フィルムの有機半導体への応用 |
| 1 | はじめに |
| 2 | DNA―脂質複合体からDNA配向化フィルムの作製 |
| 3 | DNA配向化フィルムの電導性 |
| 4 | カーボンナノチューブとの複合化 |
| 5 | 光誘起電流の観察とEL素子への応用 |
| 6 | おわりに |
|
| 3.2 | 脂質二分子膜を利用した光導電性 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 脂質二分子膜の構造と物性 |
| 2.1 | リン脂質の種類と構造 |
| 2.2 | 脂質二分子膜の形態と調製 |
| 2.3 | 脂質二分子膜の性質 |
| 3 | 脂質二分子膜を介する光誘起電子輸送 |
| 3.1 | 概要 |
| 3.2 | 二分子膜中の増感剤による電子輸送 |
| 3.3 | 水相の増感剤による電子輸送 |
| 4 | おわりに |
|
| 応用編 有機光・電子機能デバイス開発への挑戦 |
|
| 1 | 有機EL素子 |
| 1.1 | 低分子系材料を用いた有機EL開発の現状と課題 |
| 1 | 有機EL材料の開発経緯 |
| 2 | 青色発光材料 |
| 2.1 | スチリル系青色材料 |
| 2.2 | 正孔材料の改良 |
| 2.3 | 青色ホスト材料の改良 |
| 3 | フルカラー用純青材料 |
| 3.1 | フルカラー用純青材料の開発 |
| 3.2 | 純青材料の改良 |
| 4 | フルカラー用緑色発光材料の開発 |
| 5 | ディスプレイ性能の試算 |
| 6 | まとめ |
|
| 1.2 | 高分子系材料を用いた有機EL開発の現状と課題 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 非共役系高分子 |
| 2.1 | ポリイミド |
| 2.2 | ポリマー架橋 |
| 2.3 | ポリビニルカルバゾール誘導体 |
| 2.4 | 超共役系高分子 |
| 3 | 共役系高分子 |
| 3.1 | ポリフェニレンビニレン |
| 3.2 | ポリフルオレン |
| 3.3 | 新規白色発光主鎖型共役系高分子 |
| 4 | おわりに |
|
| 1.3 | Ru錯体を含むDNA高次組織体のEL発光特性 |
| 1 | はじめに |
| 2 | DNA/導電性高分子および光機能分子複合高次組織体の構造 |
| 3 | Ru錯体を含むDNA/ポリアニリン高次組織体の光電機能 |
| 4 | 将来展望 |
|
| 1.4 | デンドリマーを電荷輸送層に用いた有機電子素子の開発 |
| 1 | 高分子としてのデンドリマーと構造 |
| 2 | デンドリマーの金属集積能 |
| 3 | エレクトロニクスデバイスへの応用 |
|
| 1.5 | 塗布型燐光有機EL材料の現状と課題 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 低分子燐光材料を分散した高分子 |
| 3 | 燐光基を側鎖に有する高分子材料 |
| 4 | 燐光基コアを有するデンドリマー型材料 |
| 5 | まとめ |
|
| 1.6 | 青色EL発光を目指した新規フルオレン系ポリマーの合成 |
| 1 | はじめに |
| 2 | フルオレン系ポリマーの合成と蛍光発光 |
| 2.1 | かさ高い置換基による共役主鎖の孤立化 |
| 2.2 | 主鎖p共役の切断による凝集の抑制 |
|
| 1.7 | 有機ELの高効率化設計への提案 |
| 1 | 有機ELの発光効率と光学的効果 |
| 2 | 高色純度蛍光有機ELの高効率化設計(外部モード比の増大) |
| 3 | 横結合型色変換方式を用いた白色有機ELの高効率化設計(薄膜モード比の低減) |
|
| 2 | 有機半導体レーザ |
| 有機半導体レーザの材料・デバイス設計 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 大電流密度への挑戦 |
| 3 | 有機レーザ活性材料 |
| 3.1 | スチリルベンゼン系低閾値材料の合成とASE特性 |
| 3.2 | その他燐光材料などの可能性 |
| 4 | 電流励起可能なデバイス構造での光励起実験 |
| 5 | 高電流密度下での励起子annihilation過程 |
| 6 | まとめと今後の展開 |
|
| 3 | 有機トランジスタ |
| 3.1 | Ambipolarトランジスタ |
| 1 | はじめに |
| 2 | 吸着ガスの制御 |
| 3 | 電極の制御 |
| 4 | ゲート絶縁層の制御 |
| 5 | その他のambipolar FET |
| 6 | Ambipolar FETと発光型FET |
|
| 3.2 | デバイス構造から見た有機トランジスタ特性の現状と課題 |
| 1 | はじめに |
| 2 | トップコンタクト型有機トランジスタ |
| 2.1 | 化学的表面処理 |
| 2.2 | トランジスタ特性 |
| 2.3 | ペンタセン薄膜のAFM観察 |
| 3 | ボトムコンタクト型有機トランジスタ |
| 3.1 | 物理的表面処理と化学的表面処理 |
| 3.2 | トランジスタ特性 |
| 4 | おわりに |
|
| 3.3 | 有機EL駆動用有機TFTの設計 |
| 1 | はじめに |
| 2 | オリゴチオフェンを用いたトランジスタの作製と特性 |
| 3 | 透明電極を用いた透明なトランジスタの作製 |
| 4 | 有機トランジスタによる有機ELの駆動 |
| 5 | まとめ |
|
| 4 | 有機太陽電池 |
| 4.1 | 有機薄膜太陽電池の最近の進展〜課題および展望〜 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 有機薄膜太陽電池の特徴と課題 |
| 2.1 | 有機薄膜太陽電池の特徴 |
| 2.2 | 有機薄膜太陽電池の分類と課題 |
| 3 | 有機薄膜太陽電池の今後の展望 |
| 3.1 | 有機薄膜太陽電池の実用化の条件 |
| 3.2 | 有機薄膜太陽電池のさらなる高効率化へのアプローチ |
| 4 | おわりに |
|
| 4.2 | p-i-n接合型有機薄膜太陽電池の進展 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 有機薄膜太陽電池の研究状況 |
| 2.1 | 最適デバイス構造の構築 |
| 2.2 | ナノクリスタル電極のショットキー接合型デバイスへの導入 |
| 2.3 | p―n接合型デバイスへの応用 |
| 3 | 測定環境の不純物排除 |
| 4 | 半導体材料自体の半導体性能の向上 |
| 5 | 今後の展開 |
|
| 4.3 | ポリアニリンを用いた色素増感太陽電池の作製 |
| 1 | 導電性高分子ポリアニリンの位置付け |
| 2 | ポリアニリンを対極に用いた色素増感太陽電池 |
|
| 4.4 | 有機色素と共役系高分子の複合化による光電変換素子の作製 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 共役系高分子への色素のドープ |
| 3 | ペリレン系色素ドープ |
| 4 | DCMドープ |
| 5 | おわりに |
|
| 4.5 | 導電性高分子を用いたエネルギー貯蔵型太陽電池 |
| 1 | 導電性高分子を用いた新しいエネルギー貯蔵デバイス |
| 2 | 色素増感太陽電池とエネルギー貯蔵 |
| 3 | 導電性高分子を用いたエネルギー貯蔵型色素増感太陽電池の構造と機能 |
| 4 | セパレータの改良 |
| 5 | 電荷蓄積電極の改良 |
| 6 | おわりに |
|
| 4.6 | 自己組織化手法による導電性高分子素子成膜法 |
| 1 | はじめに |
| 1.1 | 層状構造をとるデバイス |
| 1.2 | 層状相分離現象 |
| 1.3 | ポリマーp―n接合膜 |
| 2 | 実験 |
| 2.1 | 試料の作成 |
| 2.2 | 膜構造の評価 |
| 2.3 | 電気物性測定 |
| 3 | 実験結果および考察 |
| 4 | おわりに |
|
| 5 | キャパシタ |
| 5.1 | 導電性高分子のキャパシタへの応用 |
| 1 | はじめに |
| 2 | エネルギー貯蔵メカニズム |
| 3 | 導電性高分子材料の分類、特性比較 |
| 4 | 導電性高分子を用いた次世代大容量キャパシタ |
| 4.1 | プロトンポリマー電池 |
| 4.2 | リチウムイオンキャパシタ(非対称型ハイブリッドキャパシタ) |
| 4.3 | 金属錯体高分子を用いたキャパシタ |
| 4.4 | 安定化有機ラジカルを用いた蓄電素子 |
| 5 | 導電性高分子を用いた次世代大容量キャパシタの用途・市場 |
| 5.1 | 自動車用パワーアシスト電源(大型用途) |
| 5.2 | 電力貯蔵電源(超大型用途) |
| 5.3 | マイクロキャパシタ(超小型用途) |
| 6 | おわりに |
|
| 5.2 | 導電性高分子を用いた固体電解キャパシタ |
| 1 | はじめに |
| 2 | 従来のアルミニウム電解キャパシタの課題 |
| 3 | 導電性高分子を用いた固体電解キャパシタの開発 |
| 3.1 | 耐熱・耐湿性の優れた電解重合ポリピロールの開発 |
| 3.2 | 電解重合によるポリピロール層形成プロセスの開発 |
| 3.3 | ポリピロールを用いたキャパシタの特性 |
| 3.4 | SPキャップの工業化 |
| 4 | おわりに |
|
| 6 | アクチュエータ |
| 6.1 | 導電性高分子を用いたアクチュエータの進展 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 導電性高分子の電気化学的ドーピングと電解伸縮 |
| 3 | 電解重合ポリピロールの電解伸縮 |
| 4 | ポリピロールによる蛇腹アクチュエータ |
| 5 | チューブ状ポリピロールの電解伸縮 |
| 6 | おわりに |
|
| 6.2 | 導電性高分子の形態制御 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 形態制御の基本原理 |
| 3 | 電気化学的アクチュエータ |
| 4 | 異方性電気化学的アクチュエータ |
| 4.1 | 異方性電気化学的アクチュエータの作製と湾曲現象 |
| 4.2 | 異方性電気化学的アクチュエータの湾曲機構 |
| 5 | おわりに |
|
| 6.3 | 導電性高分子を用いたペーパーアクチュエータ |
| 1 | 電気収縮機構 |
| 2 | 等張性および等尺性収縮 |
| 3 | ペーパーアクチュエータ |
| 4 | 課題と応用分野 |
|
| 7 | センサ |
| 7.1 | 柔軟体と導電性ゴムによるロボットハンド用分布型圧力センサ |
| 1 | はじめに |
| 2 | 分布型圧力センサの構造と動作原理 |
| 3 | 分布型圧力センサと計測システム |
| 4 | 実験 |
| 5 | おわりに |
|
| 7.2 | 導電性高分子/人工細胞膜を用いたストレスセンサの開発 |
| 1 | はじめに |
| 2 | メンブレン・ストレスバイオテクノロジー |
| 3 | ストレスセンシング |
| 4 | 揺らぎ/疎水性を有する有機半導体材料の設計 |
| 5 | ストレス条件でのタンパク質の構造状態認識のためのパタン解析 |
| 6 | ボトムアップ的手法および増感剤としてのリポソームの利用 |
| 7 | おわりに |
|
| 8 | ナノワイヤ |
| 8.1 | エレクトロニクスを支える分子ナノワイヤ |
| 1 | 分子エレクトロニクスとナノワイヤ |
| 2 | 連鎖重合反応制御による分子ナノワイヤ作成 |
| 3 | 分子ナノワイヤの電気伝導 |
| 4 | おわりに |
|
| 8.2 | DNAを用いたボトムアップ型ナノ配線技術 |
| 1 | ボトムアップ型ナノテクノロジーとDNA |
| 2 | ナノテクノロジー材料としてのDNA |
| 3 | 自己集合によるナノ配線 |
| 4 | 単一DNA分子の自己組織化的伸長固定化 |
| 5 | DNAの金属化 |
| 6 | まとめ |
|
| 8.3 | 分子性ナノワイヤの構築 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 有機半導体からナノワイヤへ |
| 3 | 分子の自己組織化から得られる分子性ナノワイヤ |
| 4 | おわりに |
|
| 8.4 | ナノレベルの極微配線技術 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 電気化学エピタキシャル重合 |
| 2.1 | モノマー・ヨウ素混合系 |
| 2.2 | 表面核埋込法 |
| 3 | 異種分子ワイヤの電気化学的接続 |
| 4 | おわりに |
|
| 8.5 | 分子被覆導線の電気物性 |
| 1 | はじめに |
| 2 | 分子被覆導線の作製 |
| 3 | 分子被覆導線の導電率測定 |
| 4 | おわりに |
|
| 8.6 | 新規導電性高分子ナノワイヤの創製 |
| 1 | はじめに |
| 2 | double―cylinder型高分子ブラシの設計と溶液特性 |
| 3 | 導電性高分子ナノワイヤの作製 |
| 4 | おわりに |
|
| 8.7 | 機能性ポリシランを用いた分子ワイヤ |
| 1 | はじめに |
| 2 | 剛直らせんポリシランの特徴 |
| 3 | 剛直性と屈曲性 |
| 4 | Si―H基を有するポリシランの一段階合成と固体表面固定化 |
| 5 | 電極接合技術 |
| 6 | おわりに |
|
| 8.8 | エレクトロスピニングによる共役ポリマーのナノファイバ化 |
| 1 | エレクトロスピニング |
| 2 | ポリパラフェニレンビニレンのナノファイバ化 |
| 3 | おわりに |
|
| 8.9 | π共役系有機・高分子ナノファイバの作製 |
| 1 | はじめに |
| 2 | ポリジアセチレンナノ結晶およびナノファイバの作製 |
| 2.1 | 対象化合物 |
| 2.2 | 再沈法 |
| 2.3 | 再沈法によるDCHDナノ結晶の作製 |
| 2.4 | 再沈直後からのDCHDナノ結晶の生成過程 |
| 2.5 | サイズ制御されたDCHDナノ結晶やナノファイバの作製 |
| 3 | ポリジアセチレンナノ結晶およびナノファイバの光学特性 |
| 4 | 蛍光性有機結晶の棒状ナノ結晶の作製 |
| 5 | まとめ |
|
| おわりに さらなる進化が期待される有機半導体 |
|
| 1 | はじめに |
| 2 | 有機半導体としての共役ポリマー |
| 3 | 新機能化への道 |
| 4 | 超階層制御による期待される進化とは |